Information
お知らせ・ブログ
2025/4/23
5月~7月の農繁期、販売一時中断について2024/11/5
国産紅茶グランプリ2024 入賞2024/4/29
2024年産 新茶の販売時期2024/4/29
農繁期の販売対応について2024/1/18
1/23~1/28間 イベント出張のため発送ができません

お茶への想い
昇龍園のこれまでとこれから
大正以前も当家は代々、田んぼと茶畑を有する農家でした。当時の茶収穫は手摘みで京都や大阪・奈良からも泊まり込みで摘み子さんに来てもらっていました。昭和期には祖父の彦一が茶畑の経営規模を拡大し、茶業を生業の軸としました。同時に手摘みから機械刈りに変わるなど時代とともに作業を効率化していきました。
昭和初期当時に栽培されていたお茶の樹は、地域に自生していた「在来種」。しかし、在来種は品質が一定でないという欠点があります。この問題を解決すべく高度経済成長期に全国に広まったのが、優良品種の「やぶきた」です。やぶきたが広まるにつれ在来の取引価格は下落。そのため全国の茶産地各地で在来の樹を抜いてやぶきたへの植え替えが進みました。
その流れから当園でもやぶきたを主とする栽培に切り替えながらも、在来茶園においては農薬・除草剤を使わないという栽培で生産を続けました。
特定の種類が普及すると目新しいものが求められるのは、お茶の業界に限らずさまざまな業界から感じる部分だと思います。お茶の世界もやぶきたが増えて広がり、時を経て改めて在来が脚光を浴びるようになりました。安定した風味の「やぶきた」と昔ながらの「在来」どちらも魅力的なお茶です。やぶきたでは旨味ある煎茶、香り良い親子ほうじ茶を、在来では有機栽培の爽やかな煎茶と親子ほうじ茶、そして紅茶を製造しています。これからも慣行栽培と有機栽培のそれぞれの良さを活かせるお茶づくりをしていきたいと考えています。
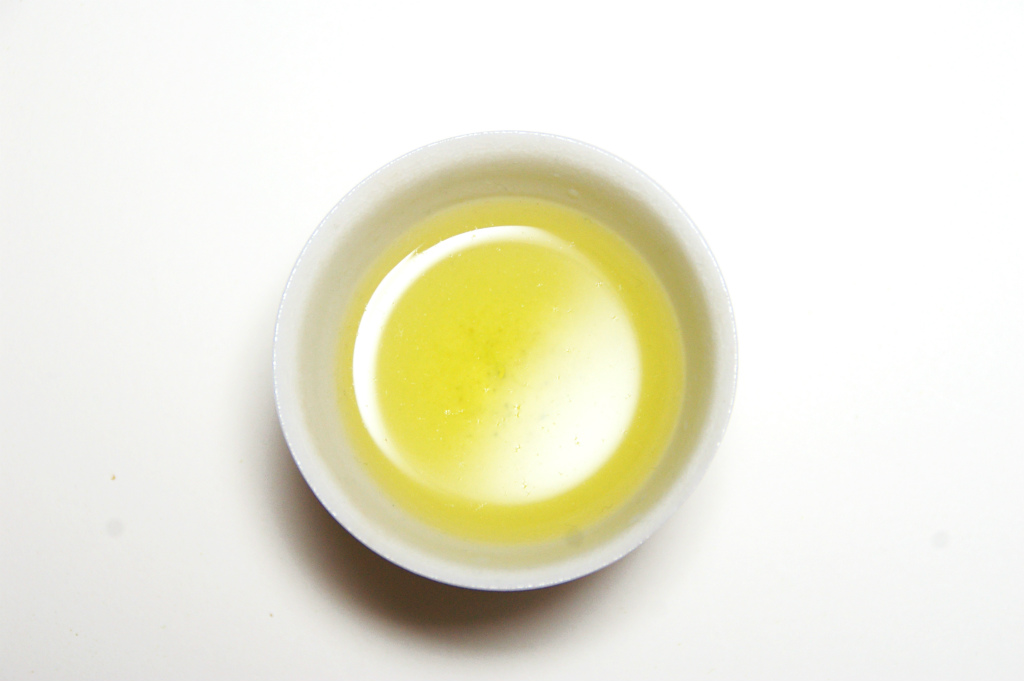
お茶農家を受け継ぐ決意
お茶農家の家に生まれたため、子どもの頃から自然と「いつかは自分が継ぐ」と思っていました。社会勉強のために就農以前に勤めていたのは、旅行会社。お茶農家と聞くと、収穫時期のみ忙しいイメージがあるかもしれませんが、管理作業は一年中必要です。そのため私は家族旅行をしたことがなく、旅行の仕事を選びました。
転機が訪れたのは、24歳の頃です。父親が体調を崩したため、退職しお茶の仕事を始めました。ただ、当時は父に言われるがまま作業をするのみ。なぜこの肥料なのか、なぜこの作業をするのか…など深く考えてはいませんでした。そういった状況でしたので父が急に亡くなった後は大変でした。肥料屋さんやJ Aさんをはじめさまざまなところに質問に行ったり、研修に参加したりしながら、少しずつ知識を蓄えていきました。これは今も継続して行っています。
毎年気候は変わる。前年度うまくいった方法も、今年同じようにうまくいくとは限らない。そう気づいたのは、自ら主となり取り組み始めてから3年が過ぎた頃でした。父が亡くなる前にもっとしっかり教えてもらっておけば…という後悔はありますが、祖父や父が残した茶畑で昇龍園のお茶をしっかりと継承していきたいと思います。

お茶への向き合い方
茶加工の原点は“手揉み茶”。製茶工場では機械が茶を揉んでいますが、機械操作のタイミングと加工方法を選ぶのは人間です。葉の状態を手で触り、確認した上で、微調整を行います。その≪感覚≫がすごく大事です。一見同じように見える茶葉も、場所や収穫のタイミングにより、違いがあります。その茶葉に対して最も適切な加工ができるよう、手揉み茶の研修に参加し茶を揉む技術や感覚を養っています。
知識と技術を高めるため全国各地に勉強に行くことで、お茶のネットワークが生まれました。SNSなどでの情報共有により、学んだ新しいやり方もたくさんあります。ただ、他の地域で成功している方法が朝宮にも当てはまるとは限りません。少しずつ取り入れ、うまくいったことは継続する。うまくいかないことは、別の方法を考える。昇龍園を受け継いでから今に至るまで、日々勉強の毎日です。

これからやっていきたいこと
≪広める≫
お茶はお湯を注ぐときの温度や時間など、いろいろな要素で風味が変わるものです。イベントでお客さんの目の前でお茶を淹れ、飲んでもらうと「おいしいね」と言っていただけます。でも、「家ではこんなに上手に淹れられない」と言われると、とても残念です。まずは煎茶の基本である“一旦お湯を冷ましてじっくり淹れる”ということをもっと多くの人に認知していただけるようにしたいと思っています。65℃・100℃のパッケージデザインのこだわりもそのひとつ。これまでお茶に馴染みがなかった世代の人にも、お茶の淹れ方(温度)を気にしてもらいつつ、リビングに置いてあっても雰囲気を壊さないようなデザインのものを作っていただきました。
基本となる淹れ方を知った上で好みに合わせて微調整し、最終的にお客さん自身が「自分の好きな味」を見つけてもらえたら嬉しいです。
コーヒー、紅茶、ジュースなどいろいろな飲み物がある中で、今日は何を飲もうかな…という選択肢のひとつに【お茶】が入れてもらえるように、いろいろな提案をしている最中です。
≪体験する≫
朝宮は焼き物の街・信楽にあり、信楽は陶器と茶の産地でもある珍しい土地です。信楽焼の茶器を使い、朝宮茶を味わうことができます。実際に信楽に来ていただいて、茶畑を案内し、お茶をのみながらお話ができる環境づくりを目指しています。

Information
お知らせ・ブログ
2025/4/23
5月~7月の農繁期、販売一時中断について2024/11/5
国産紅茶グランプリ2024 入賞2024/4/29
2024年産 新茶の販売時期2024/4/29
農繁期の販売対応について2024/1/18
1/23~1/28間 イベント出張のため発送ができません